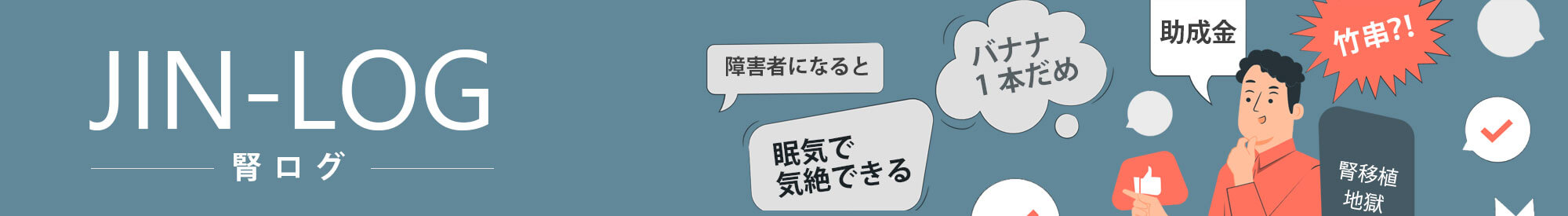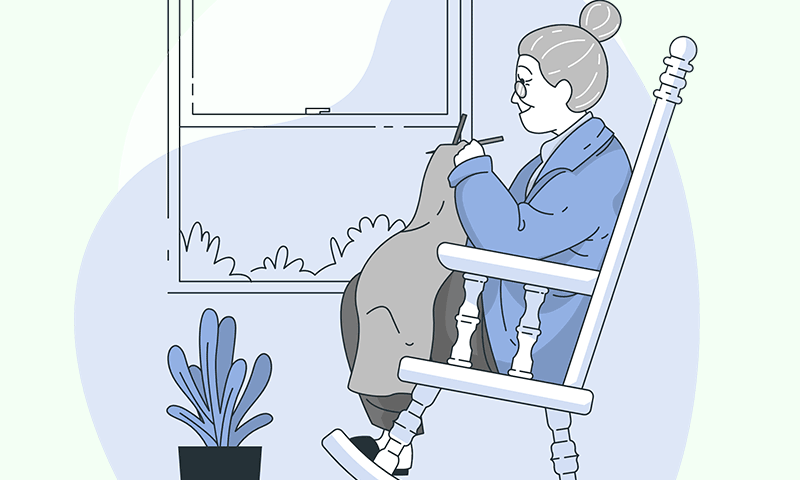人工腎臓や豚の腎臓移植の実現

最近もニュースで話題になっている、「人工腎臓」や「豚の腎臓を移植」する事につい調べてみました。
まず、「人工腎臓」の利用や、「豚の腎臓を人に移植する」という事が可能なのか。
結論:可能っぽいです。

といっても、研究段階である事には違いありません。
人工腎臓の利用について
まず、人工腎臓の場合。
定義としては「人工的に作られた腎臓」という事になります。
こちらの場合、既に「人工透析を行っている事が、人工腎臓を利用している」と言えます。
血液透析をされている方は、週3回は見る「ダイアライザ」です。
体内に埋め込むか、体外で行うかの違いで、体外で行う人工透析は日本で約35万人が利用しています。
体内で行うという研究については、「preclinical model(前臨床モデル)」で成功した事が2021年9月にカリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究チームが発表しました。
前臨床モデルの意味を調べた所、「非臨床試験」とも呼ばれていて、要するに「動物実験」です。
臨床試験が対ヒトに行う試験なので、その前段階に行う臨床試験の事を全臨床試験と呼ぶそうです。
前臨床試験は一般的にマウスを対象にするようです。
人工腎臓の体内利用
前述の通り、体内に組み込む人工腎臓の実験は前臨床モデルで成功しています。
2021年9月9日、カリフォルニア大学サンフランシスコ校が、移植可能なバイオ人工腎臓を開発。
血液のみを動力とし、体内に埋め込む形で腎臓の変わりを果たします。
この研究の凄いところは、腎移植を行った場合必須と言っても良い「免疫抑制剤」を必要としない事。
当然ながら透析も必要としないため、健常者と変わらない生活が約束されるようなものです。

英語は出来ませんが、google翻訳などを使って
頑張って和訳してみます。
一部は解釈で読み替えています。
youtube動画の翻訳

日本語にしてもむつかしい単語だらけでしたね。笑
翻訳もめちゃくちゃむつかしいです。
要約してみます。
- 腎不全患者は、近い将来、透析をしたり、いつまでも移植を待たなくてよくなる。
- バイオ人工腎臓は、免疫抑制剤を必要としない。
- 血液をろ過する機能があり、機能を維持するように最適化されている
- 生体適合性がある素材で、人体に影響が無い
- 今後、試作品をスケールアップし、人の臨床試験が行える物を作る
- 血圧のみで機器を作動させ、維持する

とまあ、こんなところでしょうか。
すごいですよね。

にぎり拳ほどの大きさの人工腎臓

余談
ちなみに、この研究には前段階に人工透析をもっと簡易化する研究を行っていました。
2020年7月。
今回発表した人工腎臓の前に、機械的操作は体外で行う「現状の透析」と似た機器の開発を行っていました。
機器自体は体内に埋め込み、小さいリュックくらいの機械と、体内に埋め込んだ人工腎臓を接続する事で透析ができる機器です。
この研究では、今まで透析に必要だった「針、大きな機械、透析バッグ、排水バッグ」などを排除し、
在宅透析をより手軽に受けられるようにするものです。
この研究でも受賞しているので、一般への普及はこちらの方が早いかもしれません。
ただ、この場合は腹膜透析のように感染症の問題は残っているのかもしれません。
腹膜透析をされている方からすると、それでも今より十分に便利なものと言えそうです。
豚の腎臓を人に移植する
豚の腎臓を人に移植する研究
2021年9月25日、米ニューヨーク大学ランゴーン医療センターで豚の腎臓を人間に移植することに成功。
実験は54時間行ったそうです。
今までに、人間以外の霊長類に対する実験はありましたが、ヒトに移植したのは今回が初。
以下の条件下で実験
- レシピエントは脳死状態で、人工呼吸器を必要とする方だった
- レシピエントの家族が実験の許可を出した
- 豚は「拒絶反応」を防ぐため遺伝子組み換えをされていた
レシピエント(移植を受けた方)は、移植から2日半の観察の後、人工呼吸器を外されて亡くなられました。
もともと、臓器提供を行いたいという意向をお持ちで、その意思をご家族が継ぎ、実験を許可されたのだと思います。
ご家族にとっては大変な決断だったと思いますが、医療の進歩に多大な貢献をされたのは素晴らしい事です。
実験結果
- 実験後、拒絶反応は見られなかった
- 老廃物を取り除き、尿を作った
54時間という短い時間ですが、正常な腎臓としての働きを見せていたようです。
移植を行ったロバート・モンゴメリー博士は以下のようなコメントをしています。
ロバートモンゴメリー博士のコメント
移植自体は、初期段階の観察だと成功という事になります。
そして、博士が言っている、コメントの3つ目と4つ目。
これは、移植を待つ人の多さと、豚を移植のために利用して良いのか、という現実の問題と倫理観の問題についてですね。
現実問題としては、腎移植を待つ方が多すぎるという事。
アメリカでは生体移植も盛んですが、それでも40%は不足しているという話。
そして、豚の命を人間の命のために利用して良いのか、という問題。
考えさせられる問題ですが、博士は
「食事や薬として既に利用しているのだから、それと変わらない事だ」と考えています。
豚の腎臓を人に移植する事の問題点
腎臓移植は、日本だと生体移植か献腎移植が行われています。
しかし、人間以外の動物の臓器を移植する事については、さまざまな問題もあります。
まず、今回の実験は「脳死」されている方に対し、「3日」という条件つきで成功したものです。
半年、1年、数年と実験した結果では無いので、今後どのようにこの課題をクリアするか、という事がそもそもの課題ですね。
そして、倫理観の問題。
今回の場合、人に移植するために「豚の遺伝子」を移植用に組み替え、それを利用しています。
その豚の腎臓を人に移植しているので、キメラを作ったという事になります。
キメラと聞くと、ギリシャ神話に出てくる
「頭がライオン、蛇のしっぽ、ヤギの体で口から火をふく」
キメラを想像してしまいます。
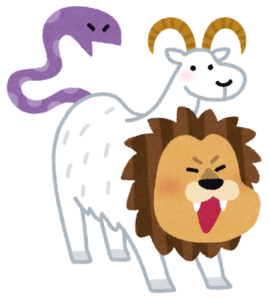
しかしキメラには2つの意味があります。
生物学的には、1つの個体に異なる遺伝子を持っている状態をさします。
キメラに対する倫理観については、まだまだ議論の余地があります。
懸念される声
これらの問題に対して、ロバート博士は「現状とさほど変わりはないじゃないか」とコメントしたという事ですね。
豚の腎臓移植については、アメリカBBCの記事を主に参考にしています。
人工腎臓や、豚の腎臓移植はいつ導入されるのか
情報を見る限り、導入は早いにこした事はありませんよね。
しかし、世の中に普及するまでには時間が必要です。
いずれも研究段階であるためです。
豚の腎移植の場合は、3日といえど人体に移植のテストが出来、その成果も良かった事は、大きな進歩だと思います。
今回のような新しい医療が、広く普及するために必要な時間を考えてみました。
普及までの時間の検討材料
- あたらしい薬の普及までの時間
- 治せない病気がなくなると言われている時期
あたらしい薬の普及までの時間
基礎研究 2~3年
薬の可能性になるものをつくる。
非臨床試験 3~5年
動物や人工的な細胞に対して、有効性と安全性、品質、安定性などを試験
臨床試験 3~7年
非臨床試験で成果が得られた物が、人に有効かを試験します。治験と呼ばれるものです。
承認申請と審査 1~2年
厚生労働省への承認申請を行います。承認がおりれば、製造・販売に至ります。

薬の場合だと、短くても9年、長くて17年くらいですね。
治せない病気がなくなる時期
実際にどうなるかは、全くもって不明です。
ただ、一説には2050年には治せない病気はほとんどなくなるのではないか、と言われています。
しかし、治せない病気が減る事で、どんどん高齢化は進みます。
高齢化が進む事で、認知症の人口は拡大します。
また、骨折する人工も増えます。
人工腎臓や、豚の腎臓移植の普及時期
人工腎臓の場合は、前臨床試験に成功した段階。
ここから、薬の開発にかかる時間をもとに、すぐに臨床試験に入ったとしても4年~9年。
アメリカで工場を作り、一般に普及し始めるのは、12年後くらいのイメージでしょうか。
ある程度、アメリカで普及してから日本に入ってくるのは、15年後。
日本で普及するのは、20年後くらいかなと思います。
豚の腎臓を人に移植する場合、臨床試験に成功した段階。
とはいえ、コチラはごくごく限定された条件下での成功です。
今から臨床試験を行う事が、至難の業。なにせ、豚の腎臓を人に移植する訳ですから、
さまざまな課題のクリアが必要になります。
これも、薬の開発と照らし合わせて考えてみます。
臨床試験だけで10年はかかりそうですよね。
そして、法的に許可されるまでに数年。やはり15年くらいはかかりそうです。
そしてコチラは、肝心の豚から腎臓は2つ取るのか、何かしらの遺伝子操作で腎臓を複数取れるようにするのかなどで、普及率は変わりそうです。
食用の豚を普通に飼育するという工程とも違うでしょうし、遺伝子操作用の豚の養豚場が必要なのか、通常の豚に人間の腎臓細胞を移植して育てるのか、など、実際はどのように行うのでしょうか。
そして、2050年
どちらの方法も15年、20年かかるという想定ですが、2050年にはほとんどの病気が治せるという説と照らし合わせて考えると、、、、、
現在が2021年ですから、2040年くらいには確かにある程度普及していそうな気がしますね。
個人的には、人工腎臓の方が普及が早そうだなと思っています。
まとめ
いかがでしたか?
人工腎臓と、豚の腎臓を人に移植する方法の2つの現在地について執筆しました。
調査を経て、どちらにもメリットとデメリットがあるように感じました。
人工腎臓の場合だと、量産化が早そうですね。
イメージ的には、だいたい20年くらいかなと予想していますが、実際にはどれくらいかかるものなのかは分かりません。
しかし、医療はどんどん進化しています。
私は今41歳で、ファミコンやレーザーディスク、フロッピーディスク、ポケベルやガラケー、ISDN、ADSLのインターネット、初代iMac、デジタルカメラなど、たくさんの進化を体験している世代に含まれると思います。
できれば生きているうちに、いろんな新しい技術を生活に取り入れてみたいのですが、
以外と早くに体験できるものが多そうでとても楽しみにしています。
今回紹介した医療も、生きているうちに当たり前になるのが楽しみです。