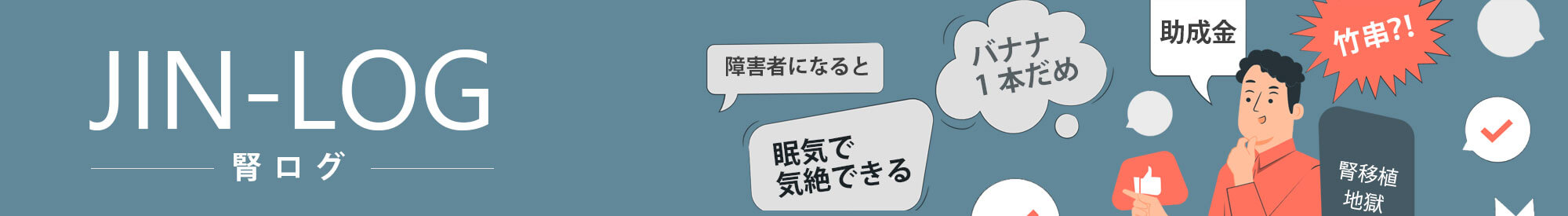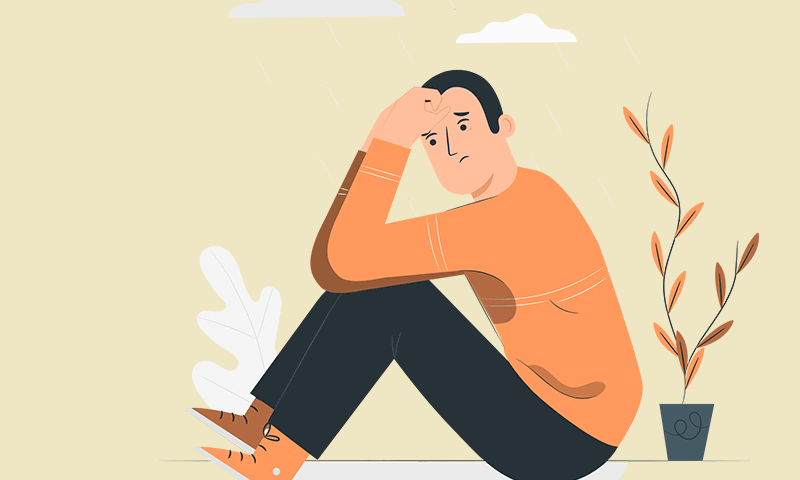透析中止で死亡した女性のニュース。真相は何だったのか。
この記事は前後半で書き分けています。
前半では事件の関係者一覧と、出来事を時系列でまとめています。
この後半記事では、出来事の詳細や背景について触れていきます。
できれば前半で概要を把握していただいてから後半をお読みください。
各出来事の詳細
腎臓病の女性患者Aさんの死亡理由(当時44歳)
Aさんの死亡理由は、透析離脱をした事。
もともと透析生活をおくっておられましたが、シャントの閉塞により緊急でシャントを管理を依頼している福生病院を緊急受診されました。
そこでAさんは、手術も透析も、もうしたくないという思いから、 透析離脱証明書 に署名。
透析を中止した事が原因で亡くなられました。
人工透析は、治療ではなく「延命措置」ですから、透析を離脱するという事は死ぬという事です。
Aさんは、この3年前にも透析がつらく、一度透析を中止していたようです。
その際も病状が悪化し、Aさんの依頼で透析を再開したという事でした。

透析は中止すると死ぬので、3年前の中止の際も透析離脱証明書に署名されているとは思います。今回と前回で違った部分はなんだったのでしょうか。
シャントの閉塞以外、違いは分かりませんでした。
3年前は再開できて、今回は再開できなかった。
そして亡くなられています。
透析離脱証明書に署名した時の状況
透析離脱証明書 に署名された時。
話し合いは、Aさん、夫のBさん、外科医、看護師、医療ソーシャルワーカー。
外科医は以下のように説明したそうです。
「血液透析は延命治療。透析をして延命をする場合、手術を行う(シャントが閉塞したので、首から透析ができる手術)。透析を継続したくないなら、手術の必要はない。その場合、寿命は2~3週間程度。選択は本人の意思次第。」
Aさんは、「透析は痛い、つらい」と普段からこぼしていたそうです。
また、車いすの生活をおくっていたため、透析の送迎を毎回夫のBさんが行っていた事に対する自責もあったとの事。
この話し合いの後、透析専門施設に移動。
透析施設の医師からは
「透析やめない方が良い。別の病院でも相談するように」と強く言われ、女性患者はパニック状態に。
Aさんは「福生病院で相談します」と答えた。
再度、 福生病院に戻り、今度はAさんとBさん、内科医とで話し合った。
Aさんは「透析はやめたいし、手術もしたくない。 2週間なのもわかっている 。」と答えた。
Bさんも「本人の希望なので、それがいいと思う」と同意した。
そして、帰路についた。
既に透析離脱から3日が経過していた。

通常、透析が3日空く事は考えられません。
3日も空くと体が相当むくみ、明らかに体感として体調が悪くなります。
水分も体内に沢山たまるので、血圧もどんどん上昇します。
Aさんの容体が悪化し、入院
自宅療養の3日目の夜、Aさんの容体が悪化。
翌朝、福生病院へ入院。
カルテに書かれた治療方針
「看取り、DNAR」。
※DNARとは、患者が心肺蘇生措置を行わない事を意思決定し、それを確認しているという事
入院初日
看護師のカルテの記載
Aさん
「 自分で決めた。でも、こんな苦しいと思っていなかった。撤回できるならしたい。無理なこともわかっている 」
入院2日目の夜
夜。AさんはBさんに「無理だとわかっているが、透析中止を撤回したい」と訴えた。
Bさんは「医師に伝える」と伝えた。
しかしBさんはその後、突然、胃潰瘍で緊急手術を受けることになった。
入院3日目
夜の間に呼吸困難になり、看護師のケアを受ける。
午前中「こんなに苦しいなら透析をしたほうがいい。 (中止は)撤回する 」と混乱しながら話したとカルテにあった。
午前中、外科医がAさんのベッドサイドへ。
※午前中ベッドサイドへ行って何をしたのかは不明。
午後、外科医がAさんに意思確認をした。
「手術するつもりはない、とにかくつらいのが嫌。取ってください」と答えたらしいが、記録は無い。
外科医の裁判での証言。
医師は「まず、つらいのを取って、正常な判断をしましょう」と昼頃、除痛の筋肉注射をした。
その後、Aさんの呼吸苦が強くなったため、鎮静を強める必要が出てきた。
家族と相談して持続静脈注射を開始したそうだが、Bさんは手術から覚めてない?はずなので、家族とは誰をさすのかはよく分からない。
病院側は落ち着いた状況で再度確認したところ、透析を希望しないとの意思を確認し、再開しなかった。
そして、17時ごろAさんは亡くなった。
裁判の争点と結果
Bさんは、Aさんが亡くなった後、助けを求めるようなメッセージが携帯電話に入っていた事に気づく。
7:50 「とうたすかかか」
入力途中の項目には「しく」の文字。
※とう、はBさんの愛称。「お父さん」という意味。
Bさんは胃潰瘍で手術を受けていたため、このメッセージに気付く事が出来なかった。

Aさんは、Bさんが緊急手術をした事を知りません。
苦しみの中、必死にメッセージを伝えたかったのだと思います。
最後を迎えるまで、メッセージはBさんに届く事はありませんでした。
Aさんが亡くなった日に、何が起きていたのか知りたくて裁判を行いました。
【裁判の争点1】 治療中止に至る経過
Bさんの意見 「治療中止に至るプロセスが不当」
入院前と入院中、医師がAさん情報提供した上で、説得するべきだった。
この意見は、以下の裁判から証拠として引用している。
法曹時報第72巻第6号(2020年)
林田医療裁判(東京高等裁判所平成29年7月31日判決、平成28年(ネ)第5668号損害賠償請求控訴事件)
中央大学法科大学院の佐伯教授の「治療の不開始・中止に対する一考察」
「 治療拒否権を認めたからといって、治療を拒否しないように説得することが権利侵害として否定されるわけではなく、むしろ説得することが医師の義務として求められている。」
「説得が繰り返し継続的になされる必要がある」
「治療を拒否する患者に、正確な情報を与え、治療を受けることを説得するまで必要である」

要約すると、透析離脱証明に署名したAさんの場合でも、まずは治療を拒否しない説得が医師の義務。
説得は繰り返し、継続する必要がある。
Aさんが拒否しても正確な情報を提供し、治療の説得が必要。
「治療中止までのプロセスが、過去の事例から鑑みても不当だ」というのがBさんの意見。
外科医の反論「パターナリスティックな見解」
「患者が治療を拒否しても、医師は治療する事を説得すべきで、それをしない事を違法とするなら、患者の自己決定権を否定するパターナリスティックな見解で不適当。」
※パターナリスティックとは、当人の意思にかかわらず、当人に変わって意思決定をする事。

要約すると
Aさんが拒否し続けたのに、Aさんの意思に関係なく説得し続けるのは医師が医師決定しているのと同じで、Aさんに決定権が無いのと同じだ。
という事。
Bさんの意見は、透析中止を決定するまでのプロセスについてなので、遠瀬離脱証明書に署名した後、AさんやBさんが透析を再開したい、という事は無関係。
あくまでも、透析中止を決定するまでの内容に不備があったのか、無かったのか、という事。
【裁判の争点2】 救命措置の不作為
Bさんの意見 「救命措置の不作為」
Aさんは透析再開の意思を看護師に伝え、カルテにも記載されていた。
そして、これは1度の意思伝達ではなく、何度か行われていた。
しかし透析は再開されなかった。
外科医の反論 「術中死亡の可能性 」
・8月9日に透析を再開できる手術ができれば、スケジュール通りの透析ができた
・8月14日に手術した場合(亡くなる前日)
8月7日から透析中止して7日経過しており、術中死亡の可能性があった。
予後、悪くなった可能性が高い。いつ心停止になってもおかしくない。

Bさんの意見は、透析を再開したいとAさんが何度も伝えたのに透析が再開されなかった事は、命を救う行為に対して消極的だという事。
外科医の反論は、透析を中止してから7日も経過していたので、手術中に死亡する可能性があった事。
手術をしても、その後容体が悪化した可能性が高く、心肺停止のリスクが高かったという事。
【裁判の争点3】 説明義務違反
Bさんの意見「説明義務違反」
透析離脱の意思は、撤回可能という説明をしなかった。
透析離脱証明書には、「撤回できる」という事が全く記載されていなかった。
Bさんは、裁判で以下のようにも話しています。
「透析手術のための入院となればと思っていた」
「AさんはBさんの言うことを聞かない。医師から説得して欲しかった」
裁判所の勧告
この件については、何度も裁判中に病院側に確認された。
そして、以下のように和解を勧告した。
「Aさんに対して、積極的に「死の選択」を誘導したとは認められない。」
「しかし、生死を決定する重大な意思決定にも関わらず、説明や意思確認が不十分だったと言える」
そして、これ以上の争いはやめて、和解するのはどうか、と勧告した。
裁判の結果
病院側もBさんも、和解する事を選択した。
和解条項
- 説明を適切に行う。また、患者の理解を得ることに努める。
- セカンドオピニオンをすすめる
- 患者が治療方針の決定を保留できる
- 患者の意思決定後も、変更できる
- 意思に変更がないか、家族等とともに確認する
- 和解金を支払う
和解金の金額は公表されなかった。

和解の勧告に至った主な理由としては、カルテに未記載の証言が出てくる事が多く、Aさんの意思決定に至るプロセスや、その後の撤回について病院側に課題はあった、という事。
問題となった世論の争点
医師は、透析離脱証明書に署名した時のAさんの意思を尊重した。
これに反論する世論がかなり多かった事。
世論の病院側の判断に対する反論理由
「やはり透析を再開したい、と署名後でもAさんが訴えたのなら、署名があっても尊重すべきだ」という事。
この世論はかなり大きく広がり、病院の判断がメディアに激しく攻撃された形になった。

前編の時系列に記載したとおり、Aさんが夫のBさんにあてたメールを見ると
どうしても私も感情的にとらえて、救えたのではないかと思ってしまいます。
しかし、透析離脱証明書に署名した時のAさんの精神状態は正常時と思われる事。
透析を再開したいと言った時のAさんは極限状態にあった事。
極限状態のAさんに透析を再開したとしても、透析離脱証明書に署名した時と同じ心境にまたAさんは逆戻りする事になります。
また、外科医の裁判での反論の通り、術中死亡した可能性や、予後の心肺停止に繋がったのかもしれません。
要するに、正常な心境で「死にたい」と願ったAさんと、その署名時に同席していた夫のBさんの意思を医者は尊重したという形。
救うという事が、生かすという事なのか、患者や関係者の意思を尊重する事なのか。
ここが世論の争点です。
まとめ
この事件について、情報をとぎれとぎれで知ったためあまり詳しく理解していませんでした。
今回、たくさんの記事などで詳細を知り、とても悲しい出来事だったという事を知りました。
そしていくつか、違和感を覚える事もありました。

透析中止の選択や説明を「外科医」が行った事。
外科医は、透析専門化ではなく、外科専門です。
もちろん外科医であっても透析を中止するリスクについて理解はしていて当然です。
でも、透析中止についての説明を外科医が行うのは通常なのでしょうか。
Aさんのパターンとしては、シャントが使えなくなったために、外科医を受診されています。
しかし、透析を中止したい、という要望について受け止めるのは通常なら透析専門医が行いそうなものです。
現に、透析専門施設では、「絶対に透析はやめてはいけない」とAさんを説得し、再度福生病院に相談するようにすすめています。
透析中止をすると死ぬという事はAさんもBさんも理解されていたと思いますが、
「どのように死んでいくのか」という所まで外科医で説明が出来たのでしょうか。

Aさんは、Bさんが緊急手術になった事を知っていたのでしょうか。
この点は、非常に気になる所です。
AさんはBさんが手術になった事を知らなかった場合、想像もできないくらいの孤独の中で亡くなった事になります。
死を選択したとしても、選択している時点で突然死にはなりづらいはず。
ある程度の死期は、容体などから分かると思います。
せめて、Bさんが緊急手術で、「手を握ったり顔を見る事が出来ない」という事が分かって亡くなる事が出来たのかが気になります。
Aさんがそれを知っていたら、携帯電話のメッセージだけでなく、医師や看護師にBさんへのメッセージを伝えられなかったのかと。
この2人のすれ違いの死はあまりに無残で、悲痛です。
せめて会えなくても、長年連れ添った事への感謝の気持ちや、愛を伝えられたのか。
この部分を想像する事が一番私にとってつらく、なんども筆が止まりました。
Aさんはただ、苦しさと孤独で亡くなられていたとしたら。Bさんがその事を想像されているとしたら。
胸が張り裂けそうです。
この一連の出来事の争点に、この点が触れられている事は見受けられませんでした。
基本的には、病院の判断が適切であったか、が裁判でも世論でも争点です。
でも私は、「最低限の幸せの中、死を迎えられたのか」という所がどうしても気になります。
医療について、私は無知です。
何が最良な選択なのかも正直な所分かりません。
でも、死ぬ事が分かっていて、準備が出来るのであれば、愛する人や大切な人達に感謝を伝えて、死を迎えたいと思いました。
「人工腎臓」や「豚の腎臓移植の研究」が、透析から人を救う時代が早くやってきますように。
そして、出来る限りの幸せの中、死を迎えられる人が1人でも多くあるように、切に願います。