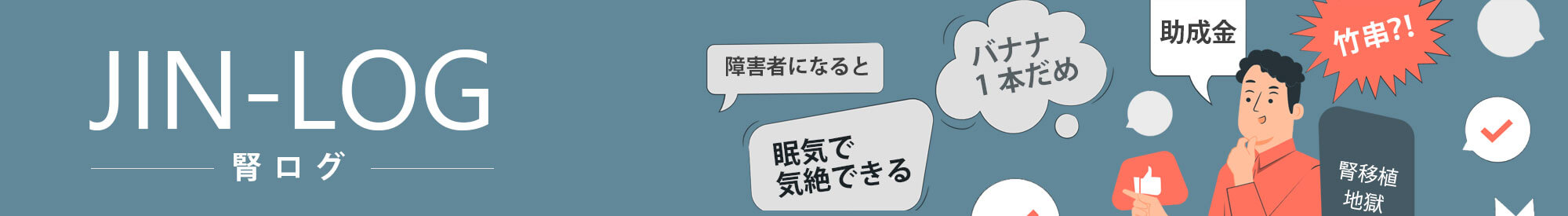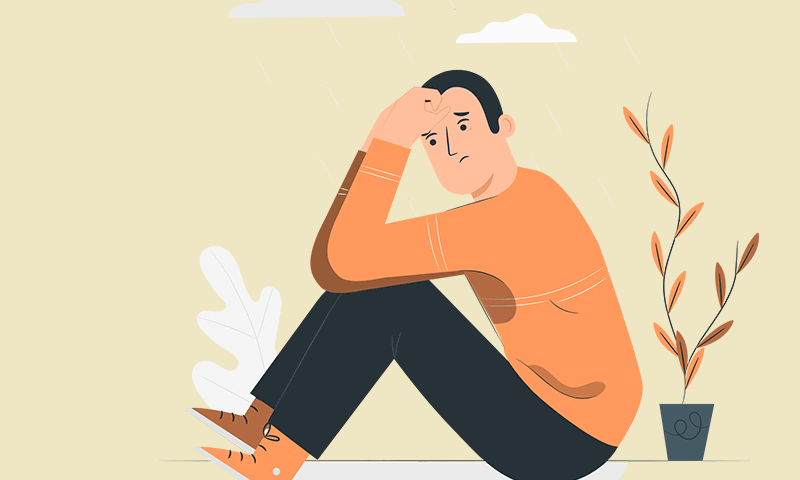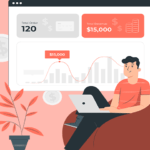透析中止で死亡した女性のニュース。真相は何だったのか。
ニュースで何度か見ていたものの、情報がとぎれとぎれに入ってきていたため、きちんと把握は出来ていませんでした。
先月初旬、病院と遺族が和解した、というニュースが出たので、真相はどういう事だったのか調べてみました。
また、この記事は「前後半」に分けて執筆していきます。
前半(本ページ)は時系列や関係者一覧などの整理。後半は、各事態の詳細について。
ニュースの概要
2021年10月5日。
透析中止によって死亡した女性の遺族が、透析を中止した病院に対して訴訟を起こしていたが和解が成立した。
遺族側は、「患者が透析中止を望んではいたが、医師は治療を説得する義務を怠った」という理由で訴訟。
病院は患者への説明、意思確認が不十分だったとして、解決金を支払った。解決金は不明。
本件の関係者

訴訟を受けた病院と透析専門施設は別である事。
亡くなった女性の夫も入院・手術を受けた時期などが重なる事。
これらが内容を少し分かりづらくしていたので、本件の関係者の一覧を記載します。
本件の関係者
- 腎臓病の女性患者Aさん(当時44歳)
- Aさんの、夫Bさん
- 公立福生病院 (シャントの管理、外科)
- 透析専門施設
- 東京地裁
- 日本透析医学会
亡くなった女性患者Aさんの概要
- 2001年 うつ病を指摘された事がある
- 2004年 糖尿病が原因で透析を開始。半年に1度シャント管理のため地域病院を受診。
- 2015年 透析施設の依頼でシャント管理のため公立福生病院を受診。
- 腹膜透析、血管内治療、人工血管はむつかしい状態。
- 2018年8月 シャント閉塞。
本件の時系列
2018年
8月9日
透析専門施設でAさんのシャント閉塞を確認。
透析専門施設から、 公立福生病院に緊急受診を依頼。
公立福生病院にてAさんはシャントの代替え手術を拒否。Aさんは透析離脱証明書に署名。
公立福生病院から透析専門施設に看取りを依頼。
※ 看取りとは、死が避けられない方の様々なケアを行い、人生の最後を支援する事
透析専門施設でAさんは透析継続を強く勧められパニックになる。
8月10日
AさんとBさんで公立福生病院を受診。看護師、医師と面談。
Aさん自宅療養へ。
8月13日
Bさんがが透析継続の説得を開始。
夜、AさんがBさんにが呼吸難を訴える。
8月14日
午前中、Aさんが公立福生病院に入院。緩和ケアの処置を受ける。
8月15日
夜、BさんがAさんの病室を出て帰路につく前に、胃痛で緊急外来へ。
8月16日
未明、Bさんは胃潰瘍で手術を受ける。手術前、BさんはAさんの主治医にAさんが透析できるよう依頼。
AさんからBさんの携帯電話に以下のメッセージ。
※この時点で、Bさんは手術麻酔から覚めていない。
7:50 「とうたすかかか」
入力途中の項目には「しく」の文字。
※とう、はBさんの愛称。「お父さん」という意味。
17時過ぎ Aさんが死亡(当時44歳)
Bさん麻酔から覚める。
Bさんの退院時
手術のため病院に携帯電話を預かってもらったBさんは、退院時に携帯電話に電源を入れ、初めてAさんからのメッセージを確認する。
2019年
3月6日
公立福生病院を監督する都が、医療法に基づいて 公立福生病院に立ち入り検査を行った。
3月7日
毎日新聞のサイトに以下の内容で記事が配信された
医師が「死」の選択肢提示 透析中止、患者死亡 東京の公立病院
3月8日
毎日新聞の一面に「透析行わず20人死亡」と記載した記事
5月31日
日本透析医学会は声明を公表
「本症例が終末期の症例とは判断できないことから、あえて判断しない」
10月17日
遺族が公立福生病院組合を被告に東京地裁に民事訴訟を提起
10月26日
都内でBさんが記者会見。 提訴の理由を語った。
2020年
4月17日
日本透析医学会は学会誌に「透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言」を発表。
7月22日
東京地裁は公立福生病院に不十分な点があったとして、改善策を約束させる和解条項と和解金の支払いを勧告。
2021年
10月5日 東京地裁で和解が成立 。
まとめ
リサーチして、とてもつらい事件だったことを初めて知りました。
旦那様がこのような状況だった事も知りませんでした。
旦那様が、亡くなった後の奥様のメッセージを見た時の気持ちや、
奥様が旦那様に会えず、不安の中お亡くなりになった事。
想像するだけでも涙がこみ上げましたし、ご本人たちの無念ははかりしれません。
しかし、福生病院の対応についても間違いとは言えない記述が散見されました。
患者は患者の意思で透析中止を選択し、医師らはこれを尊重した。
患者は、死ぬと分かっていながら、透析が色々とつらすぎるので、離脱する事を選択しています。
今回は、事態を把握するために、関係者と時系列でのみ執筆しました。
これを前編とし、後編では事態の詳細について書いていきます。
このような事が今後起きづらくするためにも、「人工腎臓」や「豚の腎臓移植の研究」にはどうしても期待してしまいます。